~技術・特許の視点から見直す日本のエネルギー戦略~
2025年度もまた電気代が上がります。経済産業省が発表した再生可能エネルギー発電促進賦課金、いわゆる「再エネ賦課金」が1kWhあたり3.98円へ引き上げられ、標準的な家庭では年間1万9104円の負担になります。再エネ導入から10年以上が経過した今、多くの人が「この仕組みは本当に持続可能なのか?」と疑問を感じ始めています。
なぜ電気代は上がり続けるのか?
電気代の高騰は再エネ賦課金だけの問題ではありません。天然ガスなどの輸入価格の上昇、円安、そしてウクライナ戦争など、国際的な要因も複雑に絡み合っています。しかし、その中でも「再エネ賦課金」は目に見える形で家計に直接響く存在です。
もともとこの制度は、再生可能エネルギーを普及させるために、太陽光や風力で発電された電気を電力会社が高値で買い取り、その費用を私たち消費者が負担する仕組みです。2012年の導入当初は「未来への投資」として歓迎されましたが、今では「実質的な増税では?」という声も上がっています。
太陽光発電は本当に“クリーン”か?
太陽光発電には「CO2を出さないクリーンな電力」というイメージがありますが、それは本当に正しいのでしょうか?
太陽光パネルの製造には大量のエネルギーが必要で、その多くは中国の石炭火力によって賄われています。国際エネルギー機関(IEA)によれば、太陽光関連の主要素材(ポリシリコンやウエハー)の95%が中国に依存しており、製造工程で大量のCO2が排出されています。
つまり、「日本に設置された太陽光パネル」は表面的には脱炭素に貢献していても、その製造段階での環境負荷が見えにくくなっているのです。
さらに、日本の国土の75%が山地であるという地形的制約もあり、メガソーラーの建設が土砂災害リスクを高めるという別の問題も出てきています。実際に230か所以上が土砂災害警戒区域内に設置されているという報道もあります。
風力発電もコストの壁に直面
洋上風力発電は、「日本の未来の切り札」として期待されていました。風力は昼夜問わず発電でき、効率も高いからです。しかし、資材価格の高騰やインフレの影響で、大手企業ですら採算が取れなくなっています。
三菱商事は、洋上風力プロジェクトで2024年度に522億円の減損損失を計上しました。風車の建設が進む前の段階でこの損失は、再エネ開発が予想以上にハイリスクなものであることを示しています。
再エネ特許はほとんどが中国
再エネ技術に関する特許の世界シェアも重要な視点です。2021年時点で、太陽光発電に関する特許の8割以上が中国に集中しているという事実があります。日本企業は製品の設置や施工では活躍しているものの、根幹となる技術や特許の面では出遅れているのが現状です。
知的財産の観点から見ても、「再エネは日本の産業を強くする」という構図が成り立たないどころか、逆に海外技術への依存を強めている側面すらあります。
“新しい発想”と特許で未来をつくるには?
では、どうすればよいのでしょうか?一つの解は、日本独自の技術力を活かした再エネ関連の特許戦略にあります。例えば:
- 傾斜地でも安全に設置できる太陽光架台の構造特許
- CO2排出量を最小化したパネル製造プロセスの特許
- 災害リスク評価AIによる最適設置場所の算出方法
- 電気料金最適化のための需給予測AIアルゴリズム
このような発明は、地理的・経済的制約が多い日本において、再エネを持続可能にする鍵となり得ます。環境だけでなく「家計」も守る再エネ技術は、今後の発明の中心テーマになるかもしれません。
最後に:再エネ賦課金は「手段」であって「目的」ではない
再生可能エネルギーの普及は、将来的に重要な目標であることは間違いありません。しかし、手段が目的化してしまえば、本末転倒です。今こそ、「本当に持続可能なエネルギーとは何か?」を見直す時期ではないでしょうか。
再エネ賦課金に対する議論は、単なる料金制度の話ではありません。それは、日本の技術、経済、安全保障、さらには暮らしのあり方すら問う、大きなテーマなのです。

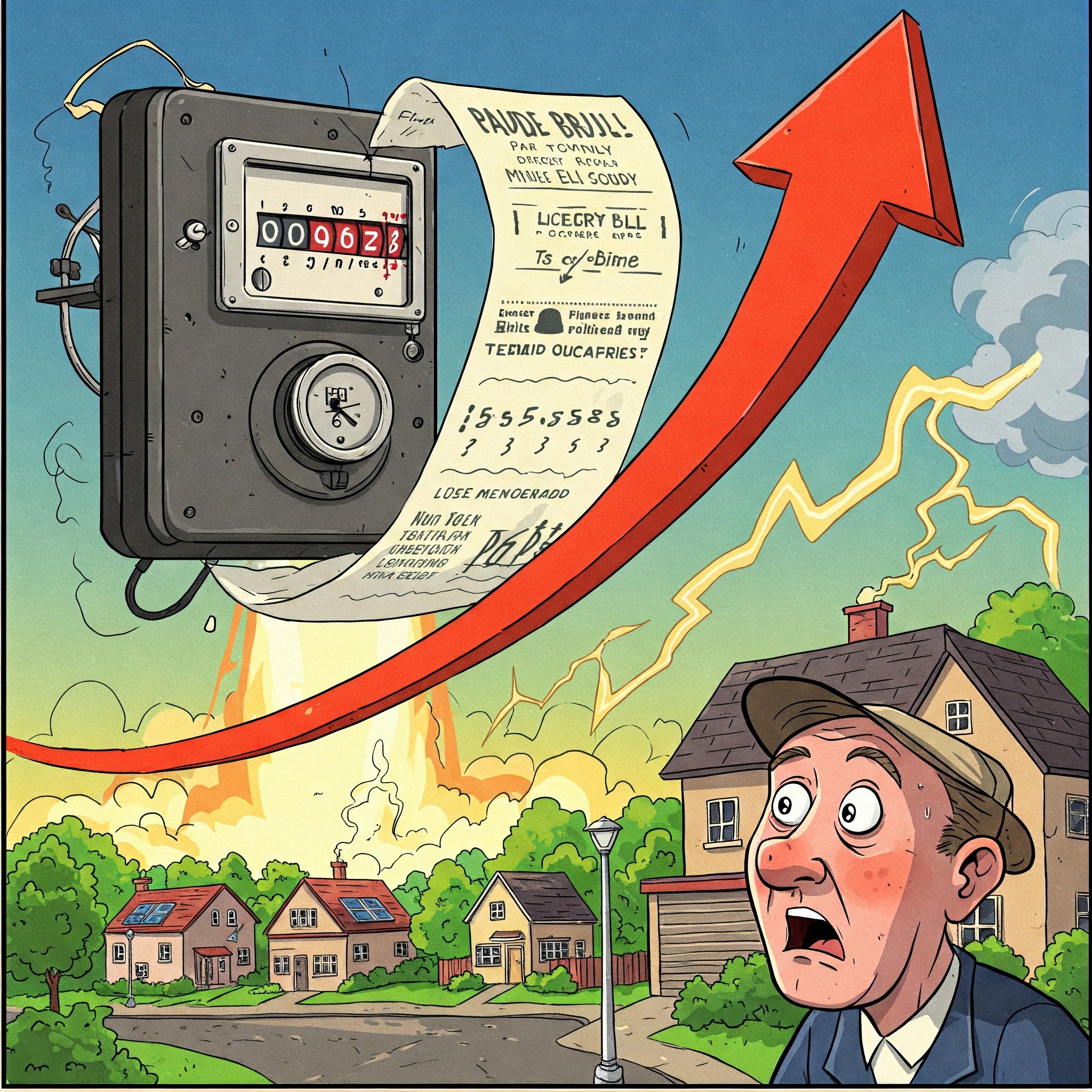
コメント