高齢になっても「頭がしっかりしているね」と言われたい。そんな思いから、クロスワードパズルを日課にしている方も多いでしょう。数字パズルの数独や、単語探しゲームも含め、「脳トレ」として長年親しまれてきました。
では、本当にこれらのパズルは脳の老化を防ぎ、認知症のリスクを下げてくれるのでしょうか?
クロスワードの効果は限定的?
2020年、学術誌『Frontiers in Human Neuroscience』で発表された研究では、クロスワードなどの言語系パズルが脳のトレーニングに使われている現状が報告されています。しかし、アメリカの医療センターの精神科医ゲーリー・スモール氏は、「パズルが万能というわけではない」と警鐘を鳴らします。
なぜなら、「脳にとってちょうどよい負荷=スイートスポット」がなければ、刺激にならないからです。簡単すぎても難しすぎても効果は薄く、慣れてしまったパズルでは効果が期待しにくくなります。
最新の研究から見える「可能性」と「限界」
2022年の医学誌『NEJM Evidence』では、**軽度認知障害(MCI)**の人に12週間クロスワードを行ってもらう実験が行われました。その結果、わずかながら認知機能の改善が見られました。さらに、2024年の『PLOS One』では、9000人以上の調査から、パズルを習慣的に行う人は、論理的思考・記憶力・言語力が高い傾向があることが示されました。
ただし、これらはあくまで相関関係であって、パズルが直接的に脳を良くするとは限らない点に注意が必要です。つまり、「頭の良い人がパズル好きなだけ」という可能性もあるのです。
鍵は「認知予備能(よびのう)」と多面的アプローチ
スモール医師は、「認知予備能」という考え方に注目しています。これは、脳に予備の力をつけることで、加齢や病気があってもパフォーマンスを維持できる能力のこと。脳をよく使う人ほどこの予備能が鍛えられると考えられています。
ただし、それでも限界はあります。2000年の『New England Journal of Medicine』に掲載された研究では、認知症リスクのある人は、記憶課題でより多くの脳の活動が必要だったことが分かりました。2年後、脳を多く使っていた人ほど認知機能の低下も大きかったという結果に──つまり、予備能には限りがあるのです。
最も効果的なのは「運動」
近年の研究では、脳を守る最強の手段として「運動」が注目されています。運動は血糖を安定させ、脳の血流を増やし、記憶を司る「海馬」のサイズを大きくすることも明らかになっています。また、**脳由来神経栄養因子(BDNF)**という物質の分泌を促進し、脳の回復力を高める効果も。
2024年に発表された『ランセット』の報告書では、認知症のリスクを下げるための「14の予防要因」が明らかにされました。運動不足、難聴、糖尿病、孤立、高血圧などがリスク因子として挙げられており、クロスワードパズルはそこに含まれていませんでした。
技術と特許の未来:脳の健康をサポートする発明とは?
ここまで見ると、「やっぱりクロスワードじゃだめか…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、パズルはあくまで一つの知的刺激として、楽しく取り入れることは良いことです。
そして、今注目されているのがAIとテクノロジーを使った脳サポート技術です。
たとえば私自身は、高次脳機能障害や認知機能低下をサポートするために、視覚情報を音声に変換するメガネ型デバイスや、脳トレーニングを自動調整するAI支援アプリなどのアイデアを、実際に特許として出願しています。
こうした技術は、「その人に合った難しさ(スイートスポット)」をAIが判断し、ゲームやクイズの内容を自動で調整する仕組みを持ちます。つまり、パズルをやるにしても、飽きずに、脳にちょうどいい刺激を与えることができるのです。
まとめ:クロスワードは「入口」、続けるなら+αを
結論として、クロスワードパズルには脳の活性化の一助となる側面はありますが、それだけに頼るのは危険です。運動、食事、社会とのつながり、そしてテクノロジーの活用といった多角的なアプローチこそが、将来の認知症予防に最も効果的な道なのです。
そして、技術者や弁理士としてできることは、「脳を守る仕組みを発明して届けること」。クロスワードをきっかけに、私たちの脳と未来について、一緒に考えてみませんか?

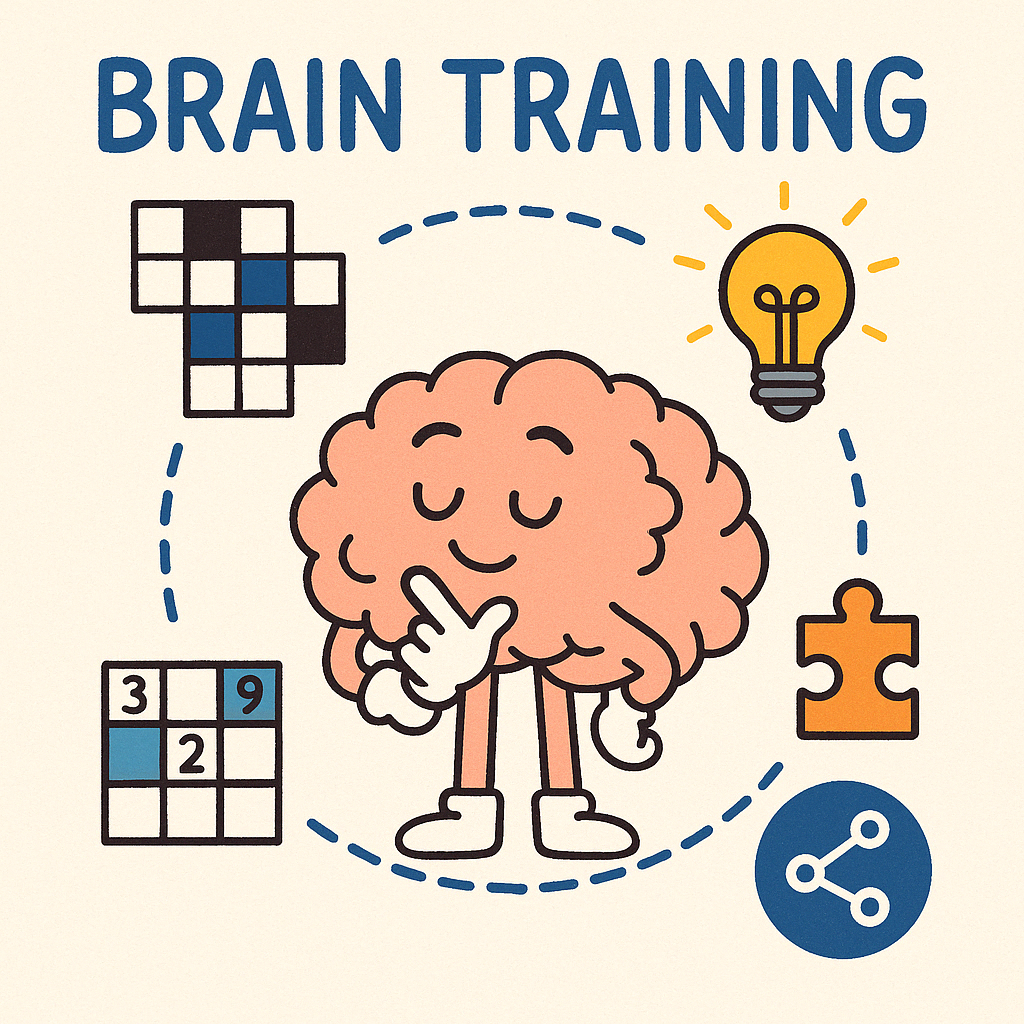
コメント