みなさんは「高次脳機能障害」という言葉をご存じでしょうか。
これは、交通事故や病気などで脳に損傷を負ったことで起こる障害です。症状は人によって異なりますが、例えば「新しいことを覚えられない」「注意が続かない」「物事をすぐに忘れてしまう」といった形で現れます。外見からは分かりにくいため、「見えない障害」とも呼ばれています。

私自身の体験と挑戦
宮崎県に住む18歳のたか子さん(仮名)は、小学生の頃に交通事故に遭い、脳を損傷しました。記憶障害や注意障害に苦しみながらも、懸命に学び続け、今年から大学で社会福祉士を目指すことになりました。
「私はこれまで、周囲からの無理解によって心無い言葉をたくさん受けてきました。でも、同じ障害を持つ人を支えたい。そのために社会福祉士になりたいと思っています」
同じ障害を持つ人だからこそ分かる苦しみや悩みを、支援の力に変えようとしています。
また、宮崎市の飛田洋平さん(42歳)は、大学生の時に事故に遭い、高次脳機能障害を負いました。記憶障害や注意障害に苦しみながらも努力を重ね、精神保健福祉士の国家試験に合格。来月から、障害者の就労支援施設で働き始める予定です。
「当事者だからこそ分かるピアサポートの力を、これからの仕事に活かしたいと思っています」
私自身の体験と挑戦
実は、私も高次脳機能障害を抱えています。脳梗塞を発症したことで失語症となり、言葉のやりとりに困難を感じるようになりました。私は弁理士として活動していますが、この経験から「障害者を支援するための特許」を考案し、特許庁へ提出しました。
しかし、個人の力だけでは限界があります。もし大きな企業がこの障害を理解し、私のような特許を活かしてくれるなら、実現の可能性はぐんと広がるはずです。実際、高次脳機能障害に関する特許はまだ200件ほどしかなく、研究や技術開発の余地は大きい分野です。
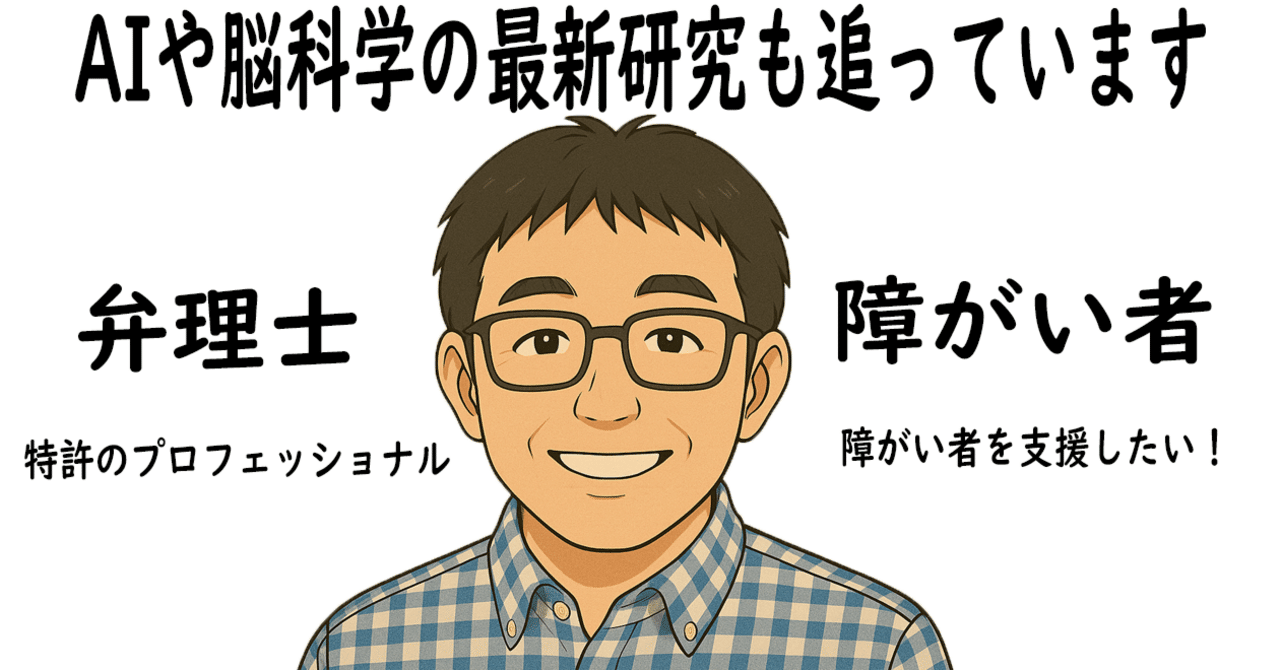
必要なのは「理解」と「仕組みづくり」
宮崎県の調査によると、県内だけでも高次脳機能障害と診断された人、あるいは疑いがある人は7,000人以上いるといわれています。しかし、自分が障害を持っていると気づいていない人も多くいます。
だからこそ、社会全体が「見えない障害」の存在を知り、理解することが大切です。
・周囲の理解があれば、当事者は少しでも生きやすくなる
・支援の仕組みが整えば、当事者も社会で活躍できる
・企業や研究者が関心を持てば、新しい技術やサービスが生まれる
こうした循環を作っていくことが、これからの課題だと私は考えています。
さいごに
「見えない障害」と向き合うことは、当事者にとって大きな挑戦です。けれど、その挑戦は必ず誰かの希望になります。
私自身も、弁理士として、そして高次脳機能障害の当事者として、できることを少しずつ形にしていきたい。大企業や社会がこの障害を理解し、一緒に歩んでくれる未来を願っています。
👉 このnoteでは、「当事者が支援する側になる挑戦」を紹介しました。
もし関心を持っていただけたら、身近な人との会話の中で「高次脳機能障害」という言葉を一度取り上げてみてください。それが社会の理解につながる第一歩になるはずです。

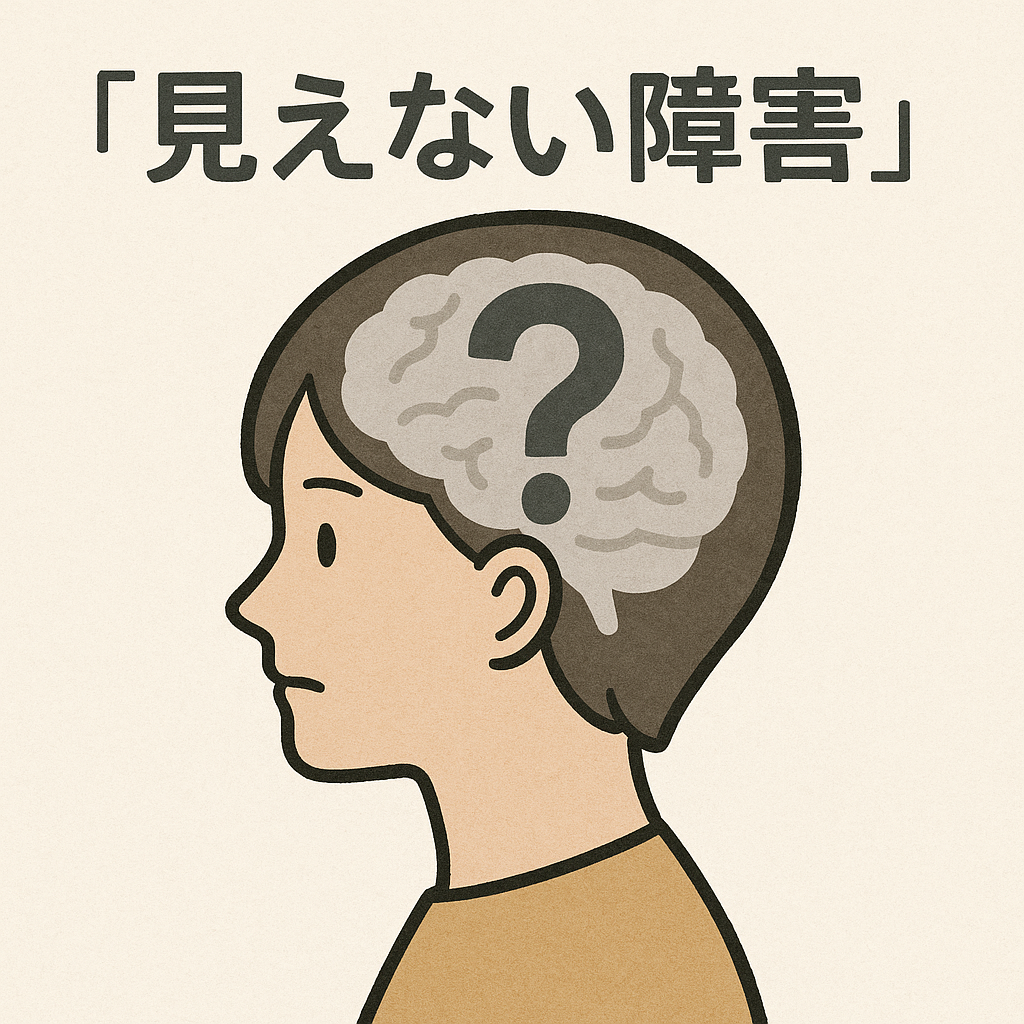
コメント